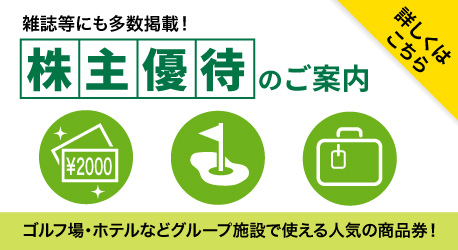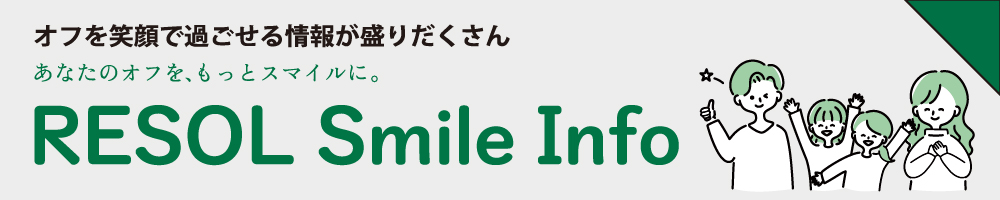【いつかは行ってみたい!】
日本の世界遺産を登録順にまとめてご紹介
あなたは日本に登録されている世界遺産がいくつあるかご存知ですか?
答えは26件(文化遺産21件、自然遺産5件)です!
これらは日本の豊かな歴史や自然、文化を表す貴重な遺産で、今インバウンド旅行者からも人気です。
そこで日本に住んでいる私たちも、その遺産がつくられた歴史や登録された背景などを知っておくことが大切です。
例えば奈良や京都などは修学旅行で行く機会が多いかと思いますが、世界遺産は日本各地にあり、なかなかすぐには行けない、行ったことが無いような地方にも!
この記事では、26件すべての世界遺産を登録順にご紹介します!
読み終わったときには世界遺産めぐりに出かけたくなっているハズ♪
①法隆寺地域の仏教建造物(奈良県)



法隆寺地域には7世紀に法隆寺や法起寺などの仏教寺院が造られ、これらの寺院では現在も宗教活動が行われています。
聖徳太子によって建立された法隆寺は、境内が西院と東院に分かれており、西院は現存する最古の木造建築群です。
一度全焼したのちに造りなおされ、現時点で約200件もの国宝・重要文化財が収められています。
法起寺は706年に完成した日本最古の三重塔のみが残っており、法隆寺の西院と同様に初期の仏教建築様式による建物です。
これらの建造物は、飛鳥時代に創建された仏教寺院建築の代表例として、中国文化の影響を受けつつも日本独自の様式を発展させたことが評価され、1993年に日本で初めて世界遺産に登録されました。
②姫路城(兵庫県)



姫路城は17世紀初頭の城郭建築の最盛期を象徴する遺産として、1993年に法隆寺とともに日本で初めて世界遺産に登録されました。
シラサギが羽を広げたような優美な姿から「白鷺城」の愛称でも知られており、城全体に塗られた白漆喰(しろしっくい)は防火や防水の効果もあります。
また、豊臣秀吉が姫路城の城主となったのちに、大阪へ拠点を移し天下統一を成し遂げたことから「出世城」とも呼ばれています。
第二次世界大戦中の空襲や阪神・淡路大震災に耐え、奇跡的に被災を免れたことでも知られています。
2026年春ごろから、市民以外の18歳以上を対象に入場料が現行の1,000円から2,000~3,000円に引き上げられる予定のため、今のうちに訪れておくのがおすすめです。
③屋久島(鹿児島県)



屋久島は白神山地とともに、1993年に日本で初めて世界自然遺産に登録されました。
屋久島の象徴でもある「縄文杉」は樹齢2,170年~7,200年と推定され、往復10時間ほどかかる登山コースです。
また、屋久島には九州最高峰の宮之浦岳(標高1,936m)をはじめとした、標高1,000mを超える山々が連なることから“洋上のアルプス”とも呼ばれています。
日本の滝百選にも選ばれている「大川の滝」は88mの落差を誇る、迫力のある滝です。
さらに有名アニメ映画の舞台にもなった屋久島では、登山だけでなくダイビングやウミガメ観察などさまざまなアウトドアスポーツを楽しむことができます。
④白神山地(青森県・秋田県)



白神山地とは青森県と秋田県にまたがる、東京ドーム約28,000個分にも及ぶ広大な山岳地帯の総称です。
人為的な影響を受けていない東アジア最大級のブナ林の中に多種多様な動植物が生息しており、“遺伝子の貯蔵庫”とも呼ばれています。
ここには東北地方を中心に古くから山岳地帯に住み、クマなどの大型獣を狩猟して生計を立てていた集団「マタギ」が1,000年以上前から暮らしていたとされています。
世界遺産地域(核心地域)の入山は特別な手続きが必要ですが、「青池」を含む十二湖を周る代表的なコースや、日本の滝百選に選ばれている「くろくまの滝」を巡るコースなど、さまざまな散策コースがあります。
⑤古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市)(京都府・滋賀県)



古都京都の文化財は、教王護国寺(東寺)・清水寺・延暦寺(比叡山)・醍醐寺・仁和寺・平等院・高山寺・西芳寺(苔寺)・天龍寺・鹿苑寺(金閣寺)・慈照寺(銀閣寺)・龍安寺・本願寺(西本願寺)・宇治上神社の14の寺院と、賀茂別雷神社(上賀茂神社)・賀茂御祖神社(下鴨神社)の2つの神社と、二条城の全17件の資産で構成されています。
これらの資産は1,000年にわたって日本の首都であった京都の歴史的・文化的価値を象徴するものとして、平安京遷都から1,200年を迎えた1994年に世界遺産として登録されました。
なかでも崖にせり出す「清水の舞台」で知られる清水寺、枯山水の石庭が有名な龍安寺、徳川家康が築城した二条城などが代表的な資産です。
⑥白川郷・五箇山の合掌造り集落(岐阜県・富山県)



両手を合わせて祈る「合掌」の形に屋根が似ていることに由来する「合掌造り」は、2月になると積雪が170cm以上にもなる豪雪地帯の自然条件に適している建築様式です。
大きな屋根の下は3~5階となっており、1階は広い居室空間、2階以上は屋根裏部屋の寝室あるいは作業空間となっています。
現在も多くの人々が生活しており、屋根の葺き替えを協力して行うなど、住民同士が助け合う「結(ゆい)」の心が大切にされています。
冬にはライトアップイベントが開催され、集落内には合掌造りの家屋に実際に宿泊できる民宿もあります。
⑦原爆ドーム(広島県)



原爆ドームは世界で唯一、原子爆弾の被害を伝える建造物で、正式名称は「広島平和記念碑」です。
もともとは広島のさまざまな物産を展示するための広島県物産陳列館として1915年に開館されました。
原爆の爆心地からわずか160mほどの距離に位置していたため、熱線と爆風を浴びて全焼しましたが、爆風が上方からほとんど垂直に働いたことにより、ドーム中心部は奇跡的に倒壊を免れました。
「原爆ドーム」という名称は、建物の頂上天蓋の残骸が傘状になっている姿から、いつの間にか市民の間で呼ばれるようになったとされています。
⑧厳島神社(広島県)



厳島神社がある宮島は島全体が神と捉えられていたため、木を切ったり土を削ったりして「ご神体」を傷つけないようにと潮の満ち引きのある場所に造られたとされています。
平安時代末期に平清盛の庇護を受け、現在の寝殿造りの壮麗な社殿群の基本が形成され、平家一門の隆盛とともに厳島神社の名も全国に広まりました。
厳島神社の象徴である大鳥居は海底に埋められておらず、地盤の強化や鳥居上部に詰め込まれた石や砂利の重みだけで立っています。
縁結びのパワースポットとしても知られ、松島(宮城県)・天橋立(京都府)と並ぶ日本三景の一つでもあります。
⑨古都奈良の文化財(奈良県)



奈良は、710年から794年まで日本の首都であり、この時代に中国(唐)との交流を通して日本文化の原型が形成されました。
古都奈良の文化財は、平城宮跡・東大寺・興福寺・春日大社・春日山原始林・元興寺・薬師寺・唐招提寺の8つの資産で構成されています。
なかでも平城京の北部中央に天皇の居所が設けられた平城宮跡、世界最大級の木造建築の大仏がある東大寺、唐の僧・鑑真が開いた唐招提寺などが有名です。
これらの資産は、東アジアとの密接な文化交流の歴史や現代にも続く日本の信仰文化を象徴しています。
⑩日光の社寺(栃木県)



日光の社寺は日光東照宮、日光山輪王寺、日光二荒山神社の二社一寺と、その周辺の石垣や階段、参道などの文化的景観を指しています。
なかでも最も有名な日光東照宮は徳川家康が祀られた神社で、三猿「見ざる、言わざる、聞かざる」の彫刻は人間の一生を表現した8面の彫刻の一部です。
日光山輪王寺は勝道上人によって開かれた日光山一帯に広がる天台宗の寺院群の総称で、3代将軍の徳川家光の霊が祀られています。
日光二荒山神社は縁結びや子授けのご利益があるとされており、「二荒(ふたら)」を音読みすると「にこう」となることから、「日光」の地名の語源となったとされています。
⑪琉球王国のグスク及び関連遺産群(沖縄県)



琉球王国のグスク及び関連遺産群は、首里城を含む5つのグスク(城跡)と4つの関連遺産で構成されています。
首里城は琉球王国の国王が追放されたのち日本軍の駐屯地や各種学校等に使用され、戦後の跡地には琉球大学のキャンパスが建てられましたが、大学移転後に首里城の復元が進みました。
しかし正殿を中心とする建造物群は、再建建造物であることから文化財としての価値が認められなかったため、首里城跡で世界遺産として登録されているのは城壁の石垣と建造物を支える石積みの土台である基壇のみになります。
首里城をはじめとしたグスクの城壁は主に珊瑚石灰岩によって造られており、曲面を多用した琉球独自の特色を備えています。
⑫紀伊山地の霊場と参詣道(三重県・奈良県・和歌山県)



紀伊山地の霊場と参詣道は、神仏習合の信仰が特徴の熊野三山・真言密教の聖地として知られる高野山・修験道の聖地である吉野・大峯の3つの霊場と、それらを結ぶ参詣道で構成されています。
紀伊山地は太古から自然信仰の地であり、伝教伝来後は山岳修行の場とされ、特に神道と仏教が融合した修験道がこの地で発展しました。
熊野三山へと続く熊野参詣道は「熊野古道」とも呼ばれ、小辺路・中辺路・大辺路・伊勢路の4つのルートから成り、熊野三山には日本三大名瀑の一つである「那智の滝」があります。
また、高野山・金剛峯寺内では真言密教の瞑想法“阿字観”や仏教の代表的な修行である写経のほか、念珠づくりも体験できます。
⑬知床(北海道)



北海道東部に位置する半島・知床は、アイヌ語で「地の果て」を意味する「シリエトク」に由来しているとされています。
知床を象徴する景勝地である知床五湖は原生林の中にたたずむ5つの神秘的な湖で、訪れる季節やヒグマ活動期によって散策条件が異なります。
また、滝自体が温泉になっている「カムイワッカ湯の滝」、滝の中ほどまで階段で登ることができる「オシンコシンの滝」など、知床には見どころスポットがたくさんあります。
1月下旬ごろに知床半島に接岸する流氷は、氷が安定する最も寒い時期の1か月半のみ開催される「流氷ウォーク」という特別なツアーなどで体感できます。
⑭石見銀山遺跡とその文化的景観(島根県)



島根県大田市にある石見銀山は、1527年に発見されたのち400年にわたって操業され、鉱山遺跡としてはアジアで初めて世界遺産に登録されました。
登録された背景としては、世界の銀産出量の約3分の1が日本の銀で占められており、その多くが石見銀山から産出されたことや環境に配慮した鉱山開発などが挙げられます。
また、石見銀山では「灰吹き法」の精錬技術が取り入れられたことで良質な銀を大量に生産することができたほか、採掘から製錬まですべて手作業で行われていたことが評価の基準となっています。
銀山本体だけでなく、鉱山集落、銀を積み出した港、それらを結ぶ街道なども構成資産に含まれており、なかでも銀山交易で栄えた温泉の港町である温泉津は日本で唯一、温泉町として重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。
⑮小笠原諸島(東京都)



小笠原諸島は、東京湾から約1,000km離れた太平洋上に位置する30あまりの島々の総称で、第二次世界大戦後にアメリカの統治下に置かれましたが、1968年に日本に返還されました。
一度も大陸と陸続きになったことがない海洋島であることから独自の進化を遂げてきた多くの固有種が生息しており、その貴重な生態系から「東洋のガラパゴス」と呼ばれています。
また、1830年まで定住者がいなかったことから「無人島(ボニン・アイランド)」とも呼ばれていましたが、現在は父島および母島に約2,400人が生活しています。
なお、それら2つの島には空港がないため、小笠原諸島への交通手段は東京・竹芝港と父島を結ぶ唯一の定期船「おがさわら丸」のみで、片道で丸1日かかります。
⑯平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群―(岩手県)



平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群―は、中尊寺・毛越寺・観自在王院跡・無量光院跡・金鶏山の5つの寺院、庭園、遺跡によって構成されています。
平泉は二度の争いを経て平和な理想社会を築こうとした奥州藤原氏の拠点です。
なかでも金色に輝く中尊寺は奥州藤原氏の初代が造営した寺院で、国宝の金色堂には藤原氏三代の遺体が眠っており、極楽浄土を具現化した代表的な建造物として知られています。
また、1689年には松尾芭蕉もこの地を訪れ、かつての栄華とその儚さに心を動かされ、句を詠んだと伝えられています。
⑰富士山―信仰の対象と芸術の源泉(山梨県・静岡県)



富士山そのものだけでなく、その周辺の神社や登山道、洞穴、樹型、湖沼など全25の資産で構成されています。
富士山は縄文時代から弥生時代にかけて形成され、噴火や溶岩の流出を繰り返していたことから恐ろしくも神秘的な山と考えられていました。
噴火を鎮めるため、8世紀後半以降に富士山の火口に鎮座する神を「浅間大神」として祀り、富士山そのものを神聖視するようになりました。
沈静化してきた平安時代後期以降は修験道の道場として利用され、江戸時代には関東を中心に「富士講」が広まり、芸術面でも世界中の多くの人々にインスピレーションを与えてきました。
⑱富岡製糸場と絹産業遺産群(群馬県)



富岡製糸場と絹産業遺産群は、富岡製糸場・田島弥平旧宅・高山社跡・荒船風穴の4つの資産で構成され、明治時代に日本の近代化と世界的な絹産業の発展に貢献したことが評価されました。
富岡製糸場内には100棟以上の建造物が現存しており、特に東置繭所は長さ104mにも及ぶ巨大な繭倉庫で、1階は事務所・作業場として、2階は乾燥させた繭を貯蔵しておく場所として使用されていました。
ここでは座操り器で繭から糸を取り、糸を木枠に巻きつける糸枠飾りづくりの体験ができます。
また、田島弥平旧宅は蚕の飼育に適した「清涼育」という換気技術、高山社跡は改良された養蚕法「清温育」を広める場所として、荒船風穴は蚕種を貯蔵するための天然の冷蔵庫とされていました。
⑲明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼, 造船, 石炭産業(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県・山口県・岩手県・静岡県)



明治日本の産業革命遺産は、製鉄・製鋼、造船、石炭産業の分野における23の構成資産群で、19世紀後半から20世紀初頭にかけて進んだ日本の産業化を象徴しています。
例えば、現在も稼働している世界遺産の一つである官営八幡製鉄所は、1901年に日清戦争の賠償金をもとに、国内で鉄から鋼材まで一貫して生産する日本初の「銑鋼一貫製鉄所」として誕生しました。
また、長崎港から船で約40分のところに位置する端島(軍艦島)は、岸壁が島全体を囲い、高層鉄筋コンクリートが立ち並ぶその外観が軍艦「土佐」に似ていることから「軍艦島」と呼ばれるようになりました。
最盛期には日本一の人口密度を誇っていたにもかかわらず、主要エネルギーが石炭から石油へと移行したことから衰退し無人島となりましたが、現在では多くの方が上陸ツアーに参加しています。
⑳ル・コルビュジェの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-(東京都)



パリを拠点に活躍した建築家のル・コルビュジェの作品のなかから、三大陸7か国(フランス・日本・ドイツ・スイス・ベルギー・アルゼンチン・インド)に所在する17の資産が世界遺産として登録されました。
ル・コルビュジェは、石積みやレンガ積みの建築が主流だった時代に、鉄筋コンクリートによる技法「ドミノシステム」を発表し、「サヴォア邸」はこの技術が最も完璧に体現された作品とされています。
ほかにも、現代の集合住宅の原型となった大規模集合住宅の「ユニテ・ダビタシオン」や、インド独立後に新しい首都として都市全体を設計した「チャンディーガル」などがあり、日本では上野にある「国立西洋美術館」の設計でおなじみです。
国立西洋美術館は、ル・コルビュジェが長年追求した「無限に成長する美術館」のアイデアを実現した世界に3つある美術館のうちの一つで、その中で最も完成度が高いと評価されています。
㉑「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群(福岡県)



日本列島と朝鮮半島の間に位置する沖ノ島は、高度な航海技術を持った宗像地域の人々にとっての道標であり、4世紀後半から9世紀末の約500年間にわたって盛んに祭祀が行われました。
そこから沖ノ島は島全体が信仰の対象である「神宿る島」とされ、入島を厳しく制限する慣習が根付きました。
女人禁制のほか、島での出来事を口外しない、島の一木一草一石たりとも持ち出さないといった禁忌が厳格に守られています。
これによりかつての遺跡がほぼ手つかずの状態で現代まで受け継がれ、その数は約8万点にも及び、そのすべてが国宝に指定されていることから「海の正倉院」とも称されています。
㉒長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産(長崎県・熊本県)



長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産は、江戸時代の禁教期(17世紀~19世紀)にかけて築かれた10の集落、キリシタンが立てこもって島原・天草一揆を起こした原城跡、日本最古の現存する教会堂の大浦天主堂の12の遺産で構成されています。
長崎と天草地方は宣教師を乗せてくる南蛮船の寄港地であったため、キリスト教が伝わった16世紀後半以降、最も集中的に宣教活動が行われました。
その結果、洗礼を受けたキリシタンたちは日本のほかの地域に比べて長期にわたって宣教師の指導を受け、キリスト教が禁じられていくなかでもひそかに信仰を続けました。
これにより、彼らのことは学術的に「潜伏キリシタン」と呼ばれるようになりました。
㉓百舌鳥・古市古墳群-古代日本の墳墓群-(大阪府)



古墳時代の最盛期であった4世紀後半から5世紀後半にかけて、当時の政治文化の中心地の一つであり、大陸に向かう航路の出発点であった大阪平野に造られた墓群です。
百舌鳥・古市古墳群は百舌鳥エリア(堺市)と古市エリア(羽曳野市・藤井寺市)に分かれており、両エリアにある全49基の古墳を指します。
本資産の古墳には前方後円墳、帆立貝形墳、円墳、方墳の4種類があり、特に百舌鳥エリアの中央部に位置する仁徳天皇陵古墳(大仙古墳)は日本最大規模の前方後円墳です。
各墳丘には円筒埴輪や葺石が施され、葬送儀礼の舞台となっていたことがわかります。
㉔奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島(鹿児島県・沖縄県)



国内最大規模を誇る亜熱帯雨林がある奄美大島、奄美群島で2番目に大きい徳之島、飛べない鳥のヤンバルクイナなどが生息する沖縄島北部、島の90%がジャングルの西表島の4つの島で構成されています。
これらは日本の国土の0.5%に満たないながら、かつて大陸とつながっていた琉球列島が分かれて島々になったという地史的背景により、国際的絶滅危惧種が95種、そのうち75種の固有種が生息するトップレベルの生物多様性を誇る地域です。
当初は「奄美・琉球」の名称で推薦されましたが、ユネスコからの名称変更要請を受けて現在の名称で世界自然遺産に登録されました。
㉕北海道・北東北の縄文遺跡群(北海道・青森県・岩手県・秋田県)



北海道・北東北の縄文遺跡群は、1万年以上にわたって採集・漁労・狩猟により定住した縄文時代の人々の生活と精神文化を伝える全17の文化遺産です。
環状列石(ストーンサークル)や土偶、墓などの遺物から、縄文時代の複雑で高度な精神文化を垣間見ることができます。
縄文時代を定住の開始・発展・成熟の過程を示す3つの大きなステージに区分したうえで、さらにそれぞれを2つに分け、各構成遺産を遺跡の構造の変遷や立地環境により分類しています。
なかでも三内丸山遺跡は、日本最多となる2,000点を超える土偶が発見されるなど、大規模な拠点集落と祭祀・儀礼の多様性を示す縄文時代最大級の集落跡です。
㉖佐渡島の金山(新潟県)



平安時代の「今昔物語」にも登場する佐渡最古の砂金山である西三川砂金山、鶴子銀山と相川金銀山の2つのエリアからなる相川鶴子金銀山で構成されています。
1601年に金が発見されると江戸幕府の成立後に佐渡奉行が置かれ、佐渡は幕府の直轄地として統治されました。
17世紀前半の最盛期には年間約400kgもの金が採れたとされる世界最大の金生産地でしたが、1989年に閉山されました。
しかし、世界中の鉱山で機械化が進むなかで、高度な手工業による採鉱と製錬技術が250年以上にわたって継続されたことが評価されています。
まとめ
日本の世界遺産をすべてご紹介しましたが、行ったことがある世界遺産はいくつありましたか?
まだ行ったことがないところがある方は全制覇を目指して、全部行ったことがある方はもう一度行きたいところを中心に、世界遺産めぐりの旅に出かけましょう!
全国に施設を展開するリソルグループ!各世界遺産の近辺にも地域によっては運営施設がございますので、お近くにお越しの際はぜひご利用ください。
https://www.resol.jp/company/facilities/
【参考文献】
文化庁.“日本の世界遺産一覧”.
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/sekai_isan/ichiran/
文化庁.“世界遺産と無形文化遺産”.文化遺産オンライン.
https://bunka.nii.ac.jp/special_content/world
リソルホールディングス(株)の株主優待
リソルホールディングスでは、株主優待として自社グループ運営施設で使える「RESOLファミリー商品券」を贈呈しています。
リソルグループの各宿泊施設でご利用いただけますので、ご滞在の際はぜひご活用ください!
株主優待制度の詳細については、以下URLをご覧ください。
https://www.resol.jp/ir/kabunushi/